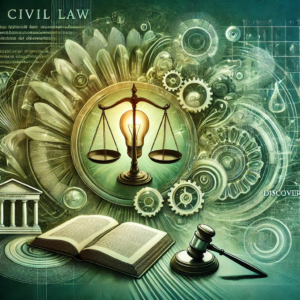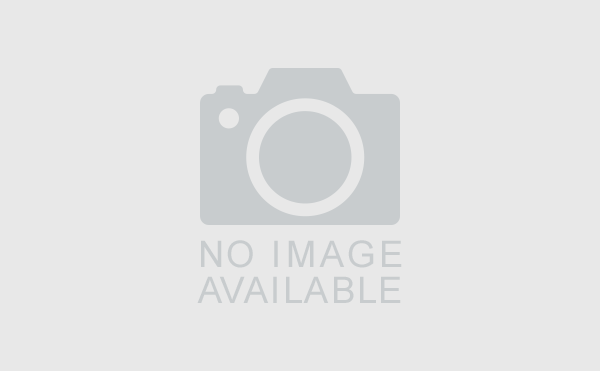債権各論④ 売買契約I──手付契約、他人物売買にかかる問題点
第1 手付(民法557条)
1 解約手付と違約手付の両立可能性
(1) 問題提起
売買契約において、違約手付の約定がある場合に、買主が売主の債務不履行がないにもかかわらず、手付金を放棄することによって、もしくは、手付倍返しを行うことによって、契約を解除することができるか。
違約手付との約定がある場合に、民法557条1項本文の規定の適用が排除されるかが問題となる。
(2) 違約手付の約定が民法557条1項の適用を排除すると考える見解(両立否定説)
違約手付として、契約違反の場合に損害賠償とは別に没収される金銭という意味 (1)で手付を交付するのは、契約の拘束力をより強いものとするためである (2)。
他方で、民法557条1項本文は、手付を解約手付と推定している (3)のであって、解約手付としての推定がなお及ぶと考えると、手付相当分を損するだけで、いつでも理由なく解除することができるようになり、かえって契約の拘束力は弱まる結果を招来する (4)。
このように、契約の拘束力を強める性質と、契約の拘束力を弱める性質が併存するのは矛盾であって妥当ではない。
そこで、違約手付との約定がある場合に、民法557条1項本文の規定の適用が排除されると考える見解がある (5)。
(3) 違約手付の約定が民法557条1項の適用をとが両立すると考える見解(両立肯定説)
しかし、当事者としては、交渉や検討を深めつつ、徐々に相互の拘束を強め、なお離脱の可能性を残したいと考えることも相当であり、その離脱の合意を尊重すべきである (6)。
また、違約手付の場合は、債務不履行があれば、手付金が没収され、または、倍額での償還が必要になる。これを同時に解約手付と解釈したところで、それとは別に手付金の放棄や倍返しにより契約を解除することができるだけであって、両立可能性が認められる (7)。
したがって、違約手付との約定がある場合に、民法557条1項本文の規定の適用が排除されるわけではない(結論を同じくする判例として、最判昭和24年10月4日民集3巻10号437頁、最判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
2 「履行に着手する」(557 条 1 項)の意義
(1) 問題提起
解約手付が交付された場合に、「相手方が契約の履行に着手した後は」契約を解除することができなくなる(民法557条1項ただし書)。そこで、「履行に着手した」といえるのはどのような場合かが問題となる。
(2) 「履行に着手した」の意義
民法557条1項の趣旨は、履行に着手した者が、不測の損害をこうむることを防止することにある (8)。
そこで、「履行に着手した」とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の 一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
【欠くことのできない前提行為であるかの判断要素】
判例は、(2)の基準をそのまま用いて適用して結論を導いているわけではなく、以下の要素を考慮しつつ具体的に判断しているのだという (9)。
履行期の到来、弁済の準備、相手方に対する履行の催告、第三者からの目的物の調達、など。
第2 他人物売買(民法561条)
1 他人物売買契約の解除までの使用利益の返還義務
|
〔設例〕中古車販売業者Y社は、Xに対し、車を売った。しかし、この車はZ社がY社に対し、所有権留保特約付きで販売したものだった。Y社が代金未払であったため、Z社は、Xの元からこの車を引き揚げた。Xは、Yに対し、権利移転義務(民法561条)違反によって、損害賠償請求をした(民法415条1項)。これに対し、Y社は、Xの自動車使用利益分についての返還請求権で相殺する旨の主張をした(最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁を参考。)。 |
(1) 問題提起
他人物の売買契約において、権利移転義務違反により解除(民法542条1項1号)された場合に、買主は、使用利益の返還義務を負うか。
(2) 解除の効果
解除の結果、給付がなかったのと同様の財産状態を回復させる必要がある。売主は代金額の利息分、買主は目的物の使用利益について、原状回復義務(民法545条1項本文)を負担することになる。
そこで、買主は、使用利益の返還義務を負うと考えるべきである(最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁〔百選II-40事件〕 (10))。
【不当利得との関係(後日調査の上追記予定) (11)】
設例の事案では、他人物売買であった以上、売主に所有権や使用収益権は存在しない。それにもかかわらず、買主がなぜそのような売主に使用利益を返還しなければならないかが疑問視されている。すなわち、売主に所有権や使用収益権がない以上は、売主との関係では少なくとも「損失」を観念することができず、不当利得の枠組みを前提とすると返還の根拠がないのではないか、ということである。
この点については、給付利得返還請求権であることを理由として、返還の根拠を肯定する見解がある。ここでいう返還請求権は、当事者間で誤ってなされた給付を巻き戻して清算する性質のものであって、売主の所有権、使用収益権の有無は関係しないという。このように、類型論をとった上で、給付利得返還請求権であると捉えれば、返還の必要があることを矛盾なく説明することができるということだろうか。
2 他人物売買後に発生した相続
|
〔設例〕父は、子の有していた土地を子に無断で第三者に譲渡した。その後、父が死亡し、子が父を相続した。 |
(1) 問題提起
被相続人が生前に相続人の財産について他人物売買を行い、相続により被相続人の履行義務(民法561条)を承継した場合に、当該相続人は、その履行義務を拒否することができないのではないか。
(2) 履行義務の拒絶の可否
相続人は、自身の財産について所有権を移転することについての諾否の自由を有している。履行義務を相続したという偶然の事情が生じたからといって、その自由を失うものと考えるべきではない。
そして、そのように考えたとしても、売主は不測の不利益を受けるわけではない (12)。すなわち、相続人が所有権移転に承諾しなければ、売主はそもそも権利を得られなかったのである。
そこで、信義則に反すると認められる特別の事情がない限り、売買契約の売主としての履行義務を拒否することができる(最大判昭和49年9月4日民集28巻6号1169頁)。
【他人物売買をした売主が権利者の地位を承継した場合】
この場合は、他人物売買をした売主は、自ら他人物売買をした以上は、権利者として履行拒絶することは信義則に反して許されない。そこで、この 場合は売買契約の売主としての履行義務を拒否することはできないと考えるべきである (13)。
- 潮見佳男『基本講義 債権各論I〔第3版〕』(新世社、2017)76頁。[↩]
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)120頁。[↩]
- 前掲・潮見基I76頁。[↩]
- 前掲・中田120頁。[↩]
- 両立否定説について、山本敬三『民法講義IV-1 契約』(有斐閣、2005)223頁参照。[↩]
- 前掲・中田契約法120頁。当該ページでは、解約手付性に関する議論として、同旨の文章が展開されている。もっとも、この議論は、解約手付との両立性を論じる上での理由づけとしても援用することができるのではないかと考えています。[↩]
- 前掲・山本225頁。[↩]
- 最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁。前掲・山本232頁。[↩]
- 前掲・中田契約法121頁。[↩]
- 最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁〔百選II-40事件〕は、次のように判示している。「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法五六一条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。けだし、解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、したがつて、買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあつたとしても、このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、相当だからである。」[↩]
- 田中教雄「他人の権利の売買の解除と買主の使用利益の返還義務」窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選II債権』(有斐閣、2023)83頁。[↩]
- 前掲・中田契約法296頁。[↩]
- 最判昭和37年4月20日民集16巻4号955頁〔百選I-32事件〕は、無権代理人が本人を相続した場面について、本人の資格に基づいて追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反する旨を判示している。このことを踏まえれば、ここでも同様に考えるべきであろう。[↩]