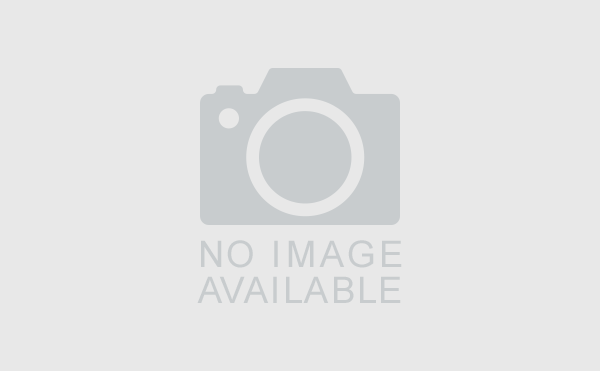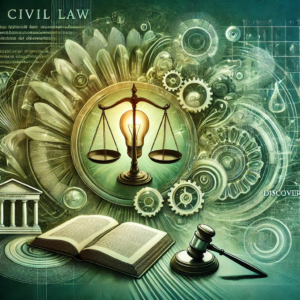Either party who is aware of information whose importance is decisive for the consent of the other must inform the other of this fact if the latter is legitimately unaware of this information or trusts his co-contractor.
However, this duty to inform does not relate to the estimation of the value of the performance.
Information which has a direct and necessary connection with the content of the contract or the capacity of the parties is of decisive importance.
The burden of proving that the other party owed him information lies with the party who claims that information was owed to him, it being for that other party to prove that he provided it.
The parties may neither limit nor exclude this duty.
In addition to the liability of the party who was bound by it, a breach of this duty to inform may result in the annulment of the contract under the conditions set out in articles 1130 et seq.
債権各論① 契約締結段階において発生しうる問題点
これから、債権各論に関する法律上の問題点について、司法試験段階で学んだ論点を中心として、再検討していきます。
私は、司法試験の段階では、判例の規範をただ覚えるだけの部分があり、正直理解していないところもあったように記憶しています。その部分も含め、数々ある論点に対して(基本的に)文献の裏付けのある適切な理由づけを加え、真の理解を目指そうというのが個人的な目的です。
現在司法試験のために学習している方にも役立つかもしれません。
構成としては、民法に関しては、判例六法に出てくる順番(基本的には、条文の順番)で整理することになると思います。
1 契約交渉の不当破棄の際に発生する責任
(1) 問題提起
契約締結過程において、契約の一方当事者が契約過程で一定の要望を行い、他方当事者がそれに応えるための出捐を行うなどの対応を経ていたにもかかわらず、一方当事者が突然交渉を破棄した場合に、他方当事者は、契約の締結過程で出捐した費用を損害賠償請求することができるかが問題となる。
(2) 契約自由の原則による帰結
確かに、契約自由の原則(民法521条1項)によれば、契約を締結するか否かは当事者の自由である。そして、契約締結がない場合には、法的な責任が成立しないのが原則である (1)。
(3) 契約準備段階に入ったことによる特別の関係性
しかし、取引を開始し、契約準備段階に入った者は、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つといえる。それゆえに、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格・財産を害しないよう配慮する信義則上の注意義務を負うものというべきである(東京地判昭和56年12月14日判タ470号145頁〔百選II-3事件の第一審〕参照)。
この注意義務に違反して相手方に損害を及ぼした場合には、信義則上の責任 (2) として、信頼利益の賠償 (3) を認めるべきである(最判昭和 59 年 9 月 18 日判時1137号51頁〔百選II-3事件〕、最判平成19年2月27日判時1964号45頁)。
【契約責任説と不法行為責任説との違いが及ぼす実益】
契約責任説をとるか不法行為責任説をとるかがなぜ問題になるのかといえば、それは消滅時効期間が異なるからである。契約責任説をとった場合には、5年間で権利が消滅し、不法行為責任説をとった場合には、3年間で権利が消滅する (4)。
契約責任説 不法行為責任説 消滅時効期間 5年間(民法166条1項1号) 3年間(民法724条1号) すなわち、契約責任説をとった場合には、責任の根拠は、民法415条の債務不履行責任となる。そのため、民法166条1項1号に基づき、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間」が経過すれば、権利が消滅する。
他方で、不法行為責任説をとった場合には、責任の根拠は、民法709条になる。そのため、民法724条1号に基づき、「被害者……が損害……を知った時から三年間」が経過すれば、権利が消滅する。
2 契約締結前の情報提供義務・説明義務
(1) 問題提起
契約交渉段階において、一方当事者が情報提供や説明を怠ったことにより、契約締結後に相手方が損害を被った場合に、損害を被った当事者は、いかなる場合に、いかなる根拠に基づく請求ができるかが問題となる。
(2) 原則論──各当事者が自身のリスクで行うべき
契約自由の原則(民法521条1項)は、契約当事者が締結しようとしている契約について、自らが必要な情報を収集して、それを検討し、判断に至ることを前提としている。その帰結として、情報収集等が不十分であった当事者は、それが錯誤・詐欺等に該当しない限りにおいては、それに伴う不利益を甘受すべきである (5)。
(3) 情報提供義務を肯定すべき理由
もっとも、自己決定の前提となる情報が整っていない場合には、正しく自己決定を行うことはできず、それは自由が真に達成されたものとは言い難い。
そして、そのような情報を入手することが困難であり、それを与えることが容易であるにもかかわらず、それを与えられていない環境においては、契約自由の原則の実質化のため、自己決定の前提となる情報は与えられる必要が高度に認められる。たとえば、当事者が専門家であったり、消費者であったりするなど、当事者間の情報格差が著しい場合には、契約締結のために必要な情報は与えられて然るべきである (6)。
また、専門家は、自身の職務に関する専門性に対する社会的信頼を前提として利益を得ている。そうである以上は、その利益に応じて社会的責任や道義的責任として、情報提供義務を負うべき場合があるのは当然である(7)。
(4) 個別判断の考慮要素
以上の観点を踏まえ、情報提供義務当事者の属性やおかれた状況、交渉の経緯、情報提供義務違反によって危険が生じる権利利益 (8)、などの諸事情を考慮した上で、個別具体的に判断すべきである (9)。
(5) 責任の性質
そして、契約締結前における情報提供義務や説明義務に違反したことによる責任の性質は、契約がまだ締結されていない段階における情報提供・説明に関する義務であること、契約の締結を左右する情報提供や説明を行う義務を当該契約に基づいて生じた義務ということができないこと (10)からすれば(11)、不法行為責任であると考えるべきである(結論は、最判平成23年4月22日民集65巻3号1405頁〔百選II-4事件〕と同旨)。
【フランス民法における情報提供義務に関する規定】
2016年改正フランス民法においては、情報提供義務に関する一般的な規定が新設された (12)。
- 池田清治『民法判例百選』〔池田〕8頁[↩]
- ただし、前掲・東京地判昭和56年12月14日判タ470号145頁〔百選II-3事件の第一審〕は、「契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である」と、契約責任説として責任を肯定するような判示をしている。その上告審である最判昭和 59 年 9 月 18 日判時1137号51頁〔百選II-3事件〕は、それを追認しているかのようである。これは、契約責任説に立ったようにも見えるものの、その性質を明言しているわけではないと説明されている(中田『新版 契約法』112頁)。その後の最判平成2年7月5日裁集民160号187頁では、不法行為責任説に立つことを明言している。[↩]
- 東京高判昭和58年11月17日〔百選II-3事件の控訴審〕では、「相手方が該契約が有効に成立するものと信じたことによって蒙った損害」として信頼利益を定義づけている。[↩]
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)113頁[↩]
- 中田裕康『債権総論〔第四版』(有斐閣、2020)147頁[↩]
- 中田裕康『債権総論〔第四版』(有斐閣、2020)150頁における情報提供義務を一般法理によって認めるとした場合の「①情報提供義務を契約自由の原則を実質的に確保するための義務」に求める見解に依拠した上で、それを具体化すべき場合として、「当事者の情報及び交渉力の格差」がある場合であると捉え、論証している。[↩]
- 角田美穂子「契約締結にかかる説明義務違反」窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選II 債権』(有斐閣、2023)10頁を参考。[↩]
- 角田美穂子「契約締結にかかる説明義務違反」窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選II 債権』(有斐閣、2023)11頁を参考。[↩]
- 最判平成23年4月22日民集65巻3号1405頁〔百選II-4事件〕千葉裁判官補足意見は、「当事者の立場や状況、交渉の経緯等の具体的な事情を前提にした上で、信義則により決められるものであ」る旨述べている。[↩]
- 最判平成23年4月22日民集65巻3号1405頁〔百選II-4事件〕は、「説明義務の違反によって生じた結果と位置づけられるのであって、上記説明義務をもって上記契約に基づいて生じた義務であるということは、それを契約上の本来的な債務というか付随義務というかにかかわらず、一種の背理であるといわざるを得ない」と判示している。すなわち、説明義務違反を債務不履行責任と構成することは、契約の前提となる説明に関する義務をそれを起点として論理的に後に生じたであろう契約それ自体に関する義務と捉えることは、原因と結果の関係を取り違えていることに着目するものといえる。[↩]
- 中田裕康『債権総論〔第四版』(有斐閣、2020)150頁の不法行為責任説の理由づけを参照。[↩]
- 中田裕康『債権総論〔第四版』(有斐閣、2020)152頁[↩]