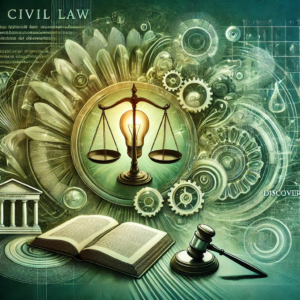債権各論② 同時履行の抗弁に関する問題点
1 代金支払債務と登記移転債務との間の同時履行関係
(1) 問題提起
不動産の売買契約において、売主が登記の移転に協力しない場合に、それを理由として買主は代金の支払を拒絶することができるか。
(2) 同時履行関係に立つ債務の考え方
双務契約は、両当事者の負担する債務が相互に対価的意義をもつと定型的に評価することのできる契約である。民法533条の趣旨は、そのような対価的意義を有する債務について、同時履行関係を認めることによって、当事者の意思を実現するとともに、公平な結果を生じさせることにある (1)。
そこで、当事者の意思や公平性を考慮した上で (2)、中心的な債務といえる債務について、同時履行関係を認めるべきである。
(3) 不動産の売買契約に関する同時履行関係
そして、不動産の売買契約においては、買主としては、所有権を取得することが中心的な目的といえる (3)。そこで、所有権の移転に資する登記の移転債務が代金支払と対価関係に立つ債務であるというべきである(大審院判大正7年8月14日民録24輯1650頁)。
したがって、売主が登記の移転に協力しない場合には、買主は代金の支払を拒絶することができる。
2 代金支払債務と目的物移転債務との間の同時履行関係
(1) 問題提起
不動産の売買契約において、売主が登記を移転したものの、目的物を引き渡さない場合に、それを理由として買主は代金の支払を拒絶することができるか。
(2) 同時履行関係に立つ債務の考え方
双務契約は、両当事者の負担する債務が相互に対価的意義をもつと定型的に評価することのできる契約である。民法533条の趣旨は、そのような対価的意義を有する債務について、同時履行関係を認めることによって、当事者の意思を実現するとともに、公平な結果を生じさせることにある (1)。
そこで、当事者の意思や公平性を考慮した上で、中心的な債務といえる債務について、同時履行関係を認めるべきである。
(3) 不動産の売買契約に関する同時履行関係
そして、不動産の売買契約においては、買主としては、所有権を取得することが中心的な目的といえる。
登記の移転がなされたのであれば、対外的にも、買主が所有権を対抗することができる状態になったといえ、所有権の取得という目的は達成されている (4)。すなわち、契約の中心的な目的達成のために、登記の移転を超えて目的物引渡債務まで実現される必要がない。そこで、目的物引渡債務と代金債務は同時履行の関係に立たないと考えるべきである。
したがって、買主は、売主が目的物を引き渡さない場合に、それを理由として代金の支払を拒絶することができない(大審院判大正7 年 8 月 14 日民録24輯1650頁)。
【引渡債務まで同時履行関係にあると考えるべきであるとする見解】
確かに、大審院判大正7 年 8 月 14 日民録24輯1650頁は、引渡債務が代金債務と同時履行の関係に立たない旨を前提としている。
しかし、その帰結はどのような場面でも絶対的にそのようにならなければならないものとはいえないと考えるべきであろう。すなわち、前述の規範に照らして、引渡債務が買主にとって、「中心的な債務」であるといえるのであれば、当事者の意思及び公平の観点から、同時履行の関係に立つと考えるべきである。
実際に、我妻栄教授も「買主が使用することを目的とする場合には、債務の重要な部分と言わねばなるまい。家屋の賣買などでは、特にそうである」と述べている (5)。
第2 賃貸借契約における同時履行
1 建物買取請求権行使時の買取代金支払義務と土地明渡義務との関係
(1) 問題提起
土地の賃借人が建物買取請求権を行使した場合に、建物買取代金請求権と賃貸人の土地明渡請求権とが同時履行の関係に立つか。
(2) 形式的な帰結
民法533条の趣旨は、対価的意義を有する債務について、同時履行関係を認めることによって、当事者の意思及び公平な結果を実現することにある。
建物買取請求権と土地明渡請求権とは、土地に関する権利と建物に関する権利という点で異なり、一見すると対価関係にあるわけではない。
(3) 売買契約類似の関係への着目
しかし、売買契約の場面において、建物の代金支払請求権と建物の明渡請求権には同時履行関係があるといえる。建物買取請求権を行使した場合には、建物について、当事者間に売買契約が成立したのと同様の利益状態が発生する (6)。そこで、当事者間には、建物買取請求権と建物引渡請求権(及びそれに付随する土地明渡請求権)との間に同時履行関係が発生する(最判昭和42年9月14日民集21巻7号1791頁 (7))
したがって、土地の賃借人が建物買取請求権を行使した場合に、建物買取代金請求権と賃貸人の土地明渡請求権とが同時履行の関係に立つといえる。
3 造作買取請求権行使時の造作買取代金支払債務と建物明渡義務との関係
(1) 問題提起
借家人が造作買取請求権を行使した場合に、借家人は、建物に備え付けた造作の買取請求権と建物明渡請求権とが同時履行の関係に立つことを理由として、建物明渡しを拒絶することができるか。
(2) 同時履行の抗弁否定説の見解
民法533条の趣旨は、対価的意義を有する債務について、同時履行関係を認めることによって、当事者の意思及び公平な結果を実現することにある。
造作買取請求権は、借地借家法33条1項に基づき、造作物の備付けによって発生した請求権であって、建物明渡請求権は、建物の賃貸借契約の終了を発生原因として発生した請求権であり (8)、両者は、発生原因を異にしている (9)。そこで、対価的意義を有する関係にはない。
そこで、借家人は、造作の買取請求権と建物明渡請求権とが同時履行の関係に立つことを理由として、建物の明渡しを拒絶することはできない(最判昭和7年9月30日大民集11巻1859頁、最判昭和29年7月22日民集8巻7号1425頁)。
【同時履行の抗弁肯定説】
もっとも、学説上は、同時履行の抗弁肯定説が有力に主張されている (10)。
造作買取請求権について、同時履行の抗弁を認めない場合には、造作どうこう以前に、まずは建物の明渡しをしなければならない。それはすなわち、造作を建物から分離した上で造作引渡しを拒絶するほかないということになる。しかし、造作を建物から分離すると、価値が損なわれることは明らかである。そもそも、造作買取請求権が認められたのは、建物から分離すると造作が価値を失うためだったはずである。したがって、同時履行の抗弁を認めないことは、造作買取請求権を認めた趣旨に反する結果を招来する。
また、造作の買取請求権とその引渡請求権との間でのみ同時履行の関係を認めるだけでは、その支払を促す効果は乏しい。造作買取請求権の実効性を確保するためには、建物についても同時履行の抗弁を認める必要がある (11)。
第3 その他の場面における同時履行
1 契約の取消しによる原状回復債務
(1) 問題提起
双務契約が取り消された場合、双方は互いに原状回復請求債務(民法121条の2第1項)を負う。両当事者の負担する当該原状回復債務は、同時履行関係にあるといえるか。
(2) 規定の趣旨からの立論
民法533条の趣旨は、対価的意義を有する債務について、同時履行関係を認めることによって、当事者の意思及び公平な結果を実現することにある。
そこで、互いに原状回復債務を負う場合についても、公平性を図る必要があるといえる場合には、同時履行関係にあると考えるべきである(最判昭和28年6月16日民集7巻6号629頁、最判昭和47年9月7日民集26巻7号1327頁は肯定している。)。
【詐欺・強迫による取消し(民法96条)の場合】
前述部分で、「公平性を図る必要があるといえる場合には」と少しお茶を濁したような記載になっているのは、別途の考慮を要すると思われる場面があるからである。特に、詐欺・強迫による取消しの場合は、別途の考慮を要する場合といえる。
詐欺や強迫の場合には、取消権者の保護の必要性が高く、詐欺や強迫行為を行ったその相手方の悪性が認められることから、同時履行の主張を制限するべきではないかと思われる(中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)158頁では、星野教授の見解が紹介されている。)。裏面から考え、同時履行の抗弁を制限しても支障がないかを検討すると、相手方は、債権の行使ができなくなるわけではなく、反訴・別訴等で対応により債権を行使することは可能である。それならば、同時履行関係を認めることによる公平性を実現する要請が強度であるとも言い難い。事例判断になるとは思われるが、相手方の悪性が強度な場合には、同時履行関係を否定する判断もありうるといえよう (12)。
2 履行の請求の際の履行の提供の意味(同時履行関係を失わせる?)
(1) 問題提起
一方の当事者が自己の債務について、一旦債務の本旨に従った履行の提供(民法493条本文)をして、相手方が受領拒絶したとする。この場合に、一方当事者が相手方に対し、債務の履行の請求をする際に、もはや履行の提供は必要ないのではないか(相手方は、同時履行の抗弁権の主張をすることはできなくなったのではないか)。
(2) 再度の履行の提供が必要
履行の提供があったとしても、双方の債務が存続する以上は、同時履行関係を認めることが当事者間の公平に資する。また、仮に、財産状態が悪化するなど、一度履行提供をした側の当事者の履行が困難になった場合に履行を強制するのは、相手方にとって著しい不利益を生じる (13)。
そこで、一方当事者が相手方に対し、債務の履行の請求をする際には、再度履行の提供をしなければならない(大審院判明治44年12月11日民録17輯772頁、最判昭和34年5月14日民集13巻5号699頁 (14))。
【相手方の受領拒絶意思が明確である場合】
相手方の受領拒絶意思が明確である場合には、もはや履行の提供をする意味はないと考えられる。
そこで、相手方が受領を拒絶する意思が明確である場合には、履行の提供すら不要となる(最判昭和41年3月22日民集20巻3号468頁 (15))。すなわち、相手方は債務不履行について、請求をした時点から、履行遅滞の責任を負う(民法412条2項)。
3 解除の際の履行の提供の意味
(1) 前提
解除が認められるためには、債務不履行が違法であることが必要である。しかし、債務者に同時履行の抗弁権がある場合には、相手方の履行がなされるのと同時に履行をすれば足りるのであって、債務不履行が正当化され、解除の要件はみたされない。
(2) 問題提起
一方の当事者が自己の債務について、一旦債務の本旨に従った履行の提供(民法493条本文)をして、相手方が受領拒絶したとする。一方当事者が民法541条に基づいて解除しようとする場合、もはや履行の提供は必要とされないのではないか。
(3) 解除の趣旨からの検討
解除の趣旨は、当事者を契約の拘束力から解放することにある。そして、解除のために履行の提供をその都度必要とすると、履行されない契約の拘束から解放されようとする当事者に過大な負担を生じさせる (16)。
(4) 相手方保護の必要性
他方で、相手方を催告の際に同時履行による牽連関係によって保護する必要もない。
仮に履行が可能になった場合は、催告に応じて履行をすれば、その履行については同時履行関係が維持されるのであるから (17)、あえて催告の際に履行の提供を要しないとしても不利益が生じないからである (18)。
(5) 結論
そこで、一方当事者が民法541条に基づいて解除しようとする場合、もはや履行の提供は必要とされない(大審院判昭和3年10月30日民集7巻871頁)。
第4 不安の抗弁権
1 問題提起
双務契約において、先履行の特約が結ばれた場合に、先履行義務を負う当事者が相手方から反対給付が受けられないおそれが生じた場合に、それを理由に自己の債務の履行を拒絶することができるか(不安の抗弁権)。
2 不安の抗弁権を認める必要性
先履行義務の合意は、相手方に対する信頼を基礎として締結されたものである。相手方が債務を履行できないおそれがある場合には、その信頼が喪失している以上、合意の前提を失ったものといえ、先履行義務を負う当事者を保護すべきであるともいえる。
3 不安の抗弁権を認めることに慎重な姿勢が必要な理由
もっとも、契約の相手方の信用状態等に関するリスクは、合意の結果である以上、自己責任の範疇であるともいえる (19)。反対給付の実現が危険となったとしても、それを安易に認めることは、自己決定の結果にそぐわない。また、相手方としても、当初見込まれた弁済がなされない場合には、更なる深刻な打撃につながる以上、不安の抗弁権は安易に認められるべきではない (20)。
4 結論
そこで、まずは、契約の締結過程等から当事者間のリスク分配について検討した上で、契約のもとで引き受けられていなかった信用不安・財産状態の悪化が生じ、反対給付が実現されない危険が現実化した場合にのみ、それを理由に自己の債務の履行を拒絶することができるものと考えるべきである (21)。
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)148頁。[↩][↩]
- 我妻栄『民法講義V1 債権各論上巻』(岩波書店、1954)93頁では、「契約の趣旨と公平の原則によつて定める」とされている。[↩]
- 双務契約においては、各当事者に複数の債務が発生する。しかし、比較的瑣末な債務についてまで同時履行を認めるのは、当事者間の公平という民法533条の趣旨に反する事態を生ずる。そのため、その契約における中心的な債務についてのみ同時履行関係を認めるべきである。この「中心的な」債務については、「対価的関係にある」「重要な」「主要な」などという表現で示されるという(中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)151頁)。[↩]
- 山本敬三『民法講義IV-1 契約』(有斐閣、2005)80頁。[↩]
- 我妻・債権各論上巻93頁。この我妻栄教授の文献が中田・契約法151頁でも参照されている。[↩]
- 山本敬三『民法講義IV-1 契約』(有斐閣、2005)612頁。[↩]
- 同判決は、「借地上の借地人所有の建物について借地人が借地法一〇条に基づく買取請求権を行使したときは、その時に右建物につき売買契約が成立し、同時に所有権移転の効力を生ずるとともに両当事者は互に同時履行の抗弁権を有するものと解すべきである(昭和二八年(オ)第七五九号同三〇年四月五日当裁判所第三小法廷判決民集九巻四号四三九頁参照)。」と判示している。[↩]
- 発生原因の違いを同時履行の抗弁権否定説の論拠として挙げている文献として、山本敬三『民法講義IV-1 契約』(有斐閣、2005)626頁。[↩]
- 発生原因の違いとして文献で言及されているものを正しく言語化できているかがわかりません。再度リサーチしたいところです。留置権に関して、否定説は造作が建物に関して生じた債権ではないことを理由としています(前掲・山本627頁)。そのことを参考にすれば、発生原因の違いという点も同様の観点から考えられるのではないかと推理しました。[↩]
- 「判例タイムズ42号」26頁以下において、前掲の最判昭和29年7月22日民集8巻7号1425頁に関する解説で、青山調査官は、次のように述べている。「前記大審院判例に対しては有力な学説が挙つて反対し(我妻・担保物権法二四頁、同氏・判例民事法昭和六年度一一事件及び昭和七年度一四五事件各評釈、石田・担保物権法論下六五一頁、勝本・担保物件法論上一一二頁、抽木・判例物権法各論一三九頁、戒能・借地借家法一二〇頁、広瀬・借地借家法二五〇頁、薬師寺・借地借家法論一九一頁、平野・継続的債権契約の特質と賃貸借及び雇傭・志林二五巻四号四〇頁等)、これらに多く聞くべきものがあるのであるから、最高裁としてはその結論はいずれにもせよもつと詳細な説明が望ましかつたと思う(もつとも、この点に関する上告理由は甚だ賴りないものであつた)。」 このように言及されるほど、学説は当時から肯定説を有力に主張していたと考えられる。[↩]
- 以上の理由づけについて、前掲・山本627頁。[↩]
- 中田・契約法158頁。[↩]
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)155頁、我妻栄『民法講義V1 債権各論上巻』(岩波書店、1954)95頁。[↩]
- 本来の債務の履行ではなく、その履行の提供をしたにすぎない場合については、双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない(司法研修所『4訂 紛争類型別の要件事実』(法曹会、2023)9頁)。[↩]
- 同判決は、「双務契約において、当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思が明確な場合には、相手方において自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である。」と判示している。[↩]
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)155頁。[↩]
- 「2 履行の請求の際の履行の提供の意味」で述べたとおりである。[↩]
- 我妻栄『民法講義V1 債権各論上巻』(岩波書店、1954)163頁参照。[↩]
- 潮見佳男『基本講義 債権各論I〔第3版〕』(新世社、2017)44頁。[↩]
- 中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)160頁。[↩]
- 前掲・潮見45頁。[↩]