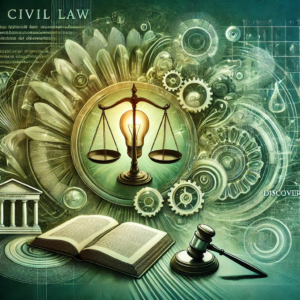債権各論③ 契約の解除に関する問題点
1 期限の定めのない債務の二重の意味での催告の可否
【催告解除の要件事実】
債務不履行解除(催告解除。民法541条本文) ① 催告
② 相当期間の経過
③ 解除の意思表示
(1) 問題提起
期限の定めのない債務については、債務者が遅滞に陥るのは、履行の請求(催告)を受けたときである(民法412条3項)。
催告解除(民法541条本文)の要件として、「催告」が要求されているが、債務者を遅滞に陥らせるための催告と、解除の効果を発生させるための催告とは、1度で兼ねることができないか。
(2) 両者の催告の関係性
債務者が履行遅滞にあることは、解除権発生の要件(民法541条本文)であるにとどまり、債権者が契約の解除のために催告を行うための要件であるとはいえない (1)。それならば、債務者を遅滞に陥らせるための催告と、解除の効果を発生させるための催告とは、論理的に前後関係がなければならない性質のものではない。
そこで、債務者を遅滞に陥らせるための催告と、解除の効果を発生させるための催告とは、1度で兼ねることができると考えるべきである(大審院判大正6年6月27日民録23輯1153頁)。
2 複合的契約の一部に債務不履行があった場合の解除の可否
(1) 問題提起
当事者間において交わされた契約が形式上2つ以上の契約から成り立っている場合を前提とする。それら一方の債務に不履行があったことを理由として、他方の契約についても併せて解除することができるか。
(2) 原則形の理解
契約が複数ある場合には、その契約の一部に解除事由があったとしても、別個の契約である以上は、他の契約の解除はできないのが原則である。
(3) 例外(密接不可分性)
もっとも、複数の契約が密接不可分か関係性を有しており、契約の目的が全体として達成されない場合には、当事者を契約の拘束力から解放する必要性が認められる (2)。当事者を達成不能な解約に拘束するのは取引通念上合理性を欠いているためである。
そこで、複数の契約の目的が相互に密接に関連づけられており、社会通念上、いずれかの契約が履行されるだけでは、契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合は、一方の債務に不履行があったことを理由として、他方の契約についても併せて解除することができる(最判平成8年11月12日民集50巻10号2673頁)。
3 解除の不可分性と管理行為
(1) 問題提起
数人の共同所有に係る不動産の賃貸借契約を解除することは、共有物の管理行為(民法252条)にあたる (3)。そのため、解除をするか否かは、持分過半数で決することができる。他方で、これは、解除権不可分の原則(民法544条 1 項)に抵触しないか。
【解除権不可分の原則】
解除権不可分の原則とは、契約の当事者の一方が数人いる場合には、数人により解除するときはその全員から、数人に対して解除するときはその全員に対して、解除しなければならないという原則をいう(民法544条1項)。
(2) 判例の見解
共有物の管理についての解除の決定は、共有者の持分価格に従って行うのが相当である。仮に、全員で解除権の行使をしなければならないとすると、管理行為を行うことが実質上困難になる場合があり、妥当ではない (4)。
そこで、民法544 条 1 項は適用排除され、民法252条が特則に当たる(最判昭和39年2月25日民集18巻2号329頁)。
したがって、持分過半数で決することは、解除権不可分の原則(民法544条 1 項)に抵触しない。
4 解除による原状回復義務と保証の範囲
(1) 問題提起
売買契約を締結した場合に、代金債権を被担保債権とする保証契約(民法446条)も締結していたとする。その売買契約が解除によって消滅した場合に、原状回復義務(民法545 条 1 項)までも保証契約による保証の範囲に含まれるか。
(2) 直接効果説
解除の趣旨は、債務不履行によって契約を維持する利益・期待を失っている解除権者を契約の拘束力から解放する点にある (5)。
そこで、解除によって、契約に基づく法律関係は、契約締結時に遡って消滅する(直接効果説 (6))。
(3) 直接効果説からの形式的帰結
契約の効果が遡及的に消滅するのであれば、原状回復義務は消滅した契約本来の債務とは別個である以上、保証債務は、原状回復義務に及ばないということになる。
(4) 保証契約を締結した当事者の意思
売買契約における売主のための保証は、通常は、その契約当事者として負担する一切の債務を保証し、その契約の不履行によって相手方に損害を被らせないことを趣旨としていると考えられる。
そこで、原状回復義務(民法545 条 1 項)までも保証契約による保証の範囲に含まれる(最大判昭和40年6月30日民集19巻4号1143頁)。
5 「第三者」(民法545条1項ただし書)の主張①──「第三者」の意義
(1) 問題提起
第三取得者に対して、所有権に基づいて目的物返還請求をする場合であっても、その第三取得者が「第三者」(民法545条1項但書)に該当する場合には、権利を害することができない。ここでいう「第三者」とはどのような者をいうのか。
(2) 直接効果説及び民法545条1項ただし書の意味
解除の趣旨は、債務不履行によって契約を維持する利益・期待を失っている解除権者を契約の拘束力から解放する点にある。そして、解除によって、契約に基づく法律関係は、契約締結時に遡って消滅する(直接効果説)。
民法545条1項ただし書は、解除の遡及効によって第三者が不測の損害を被ることを避けて第三者を保護するため、解除の遡及効に特に制限を加えた規定である (7)。
(3) 「第三者」の意義
そこで、「第三者」とは、解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除までに新たな権利を取得した者をいう (7)。
【善意の要否】
「第三者」(民法545条1項ただし書)として保護されるためには、債務不履行及び解除原因についての善意は要求されていない。
その理由としては、解除が問題となる契約では、契約そのものに瑕疵はなく、効果面においてまったく問題のない契約が締結されているのであって、その基礎の上に登場した第三者は取引において合理的に行動したものと捉えられるべきであること (8)、明文上善意が要求されていないことなどが挙げられる。
【登記の要否】
「第三者」(民法545条1項ただし書)として保護されるためには、権利保護資格要件としての登記を具備することを要求する見解が多い。
その理由として考えられるのは、不動産については、民法が特に静的安全を尊重している以上、自己の権利の保護を受ける資格として、第三者に登記を求めることは妥当であると考えられるからである (9)。
6 「第三者」(民法545条1項ただし書)の主張②──解除後の第三者との関係
(1) 「第三者」の意義からの帰結
「第三者」(民法545条1項ただし書)は、解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除までに新たな権利を取得した者をいう (7)。
それでは、解除権者と第三取得者との関係性はどのようになるか。
(2) 対抗関係で処理する見解
解除によって、解除の対象になった契約の処分的効果は遡及的に消滅する(直接効果説)。そこで、物権はもともとの状態、すなわち、解除権者に帰属する。他方で、第三取得者についても、契約によって所有権を取得している。
このように、両立し得ない物権相互間の優先的効力が問題となっている場面であるため (10)、解除権者は、解除後に物権復帰の登記を具備できるのにこれを怠っており、二重譲渡の場合と同様に、その権利主張ができなくてもやむを得ない (11)。
そこで、対抗要件の具備によって画一的に処理すべきである(最判昭和35年11月29日民集14巻13号2869頁 (12))。
そこで、解除権者及び第三取得者は、相手方に対し、対抗要件の抗弁及び対抗要件具備の抗弁を主張することができる(民法177条、178条)。結果として、対抗要件を具備しているかどうかによって、優先関係が決せられることになる。
【直接効果説の難点】
直接効果説においては、解除によって、契約の効果は遡及的に消滅する。それならば、もともと解除権者から二重譲渡を行った者に対して権利は移転していないのであって、それは裏返すと、二重譲渡を行った者から解除権者への復帰的物権変動も観念することができない (10)。
その意味で、対抗要件によって決すべきであるという結論を導くことはやや難しい点がある。しかし、上記のように考えるのであれば、対抗関係にあるとする立論を取ることも可能だそうだ。
- 我妻栄『民法講義V1 債権各論上巻』(岩波書店、1954)155頁。中田裕康『契約法〔新版〕』(有斐閣、2021)203頁も我妻教授の文献を引用している。[↩]
- 山本敬三『民法講義IV-1 契約』(有斐閣、2005)182頁では、後掲・最判平成8年11月12日民集50巻10号2673頁の調査官解説の要旨が述べられている。それによれば、ここで本質的に重要なのは、契約の個数の捉え方というよりもむしろ、「契約当事者がどのような目的で何を約定したか」という点にあるという。[↩]
- 中田・220頁[↩]
- 安永正昭『講義 物権・担保物権法〔第4版〕』(有斐閣、2021)192頁の注11を参考にして立論しました。[↩]
- 潮見佳男『基本講義 債権各論I〔第3版〕』(新世社、2017)51頁。[↩]
- 前掲・潮見基I60頁[↩]
- 前掲・中田234頁。[↩][↩][↩]
- 前掲・潮見基I60頁。[↩]
- 前掲・中田238頁。[↩]
- 前掲・中田236頁。[↩][↩]
- 鶴藤倫道「解除と登記」窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選I 総論・物権〔第9版〕』(有斐閣、2023)107頁。[↩]
- 最判昭和35年11月29日民集14巻13号2869頁は、次のように判示している。「不動産を目的とする売買契約に基き買主のため所有権移転登記があつた後、右売買契約が解除せられ、不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて、その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘らないことは、大審院屡次判例の趣旨とする所である。」[↩]